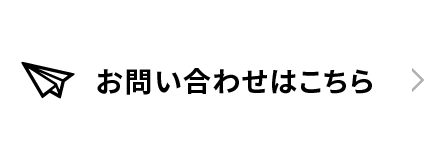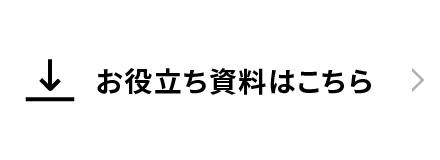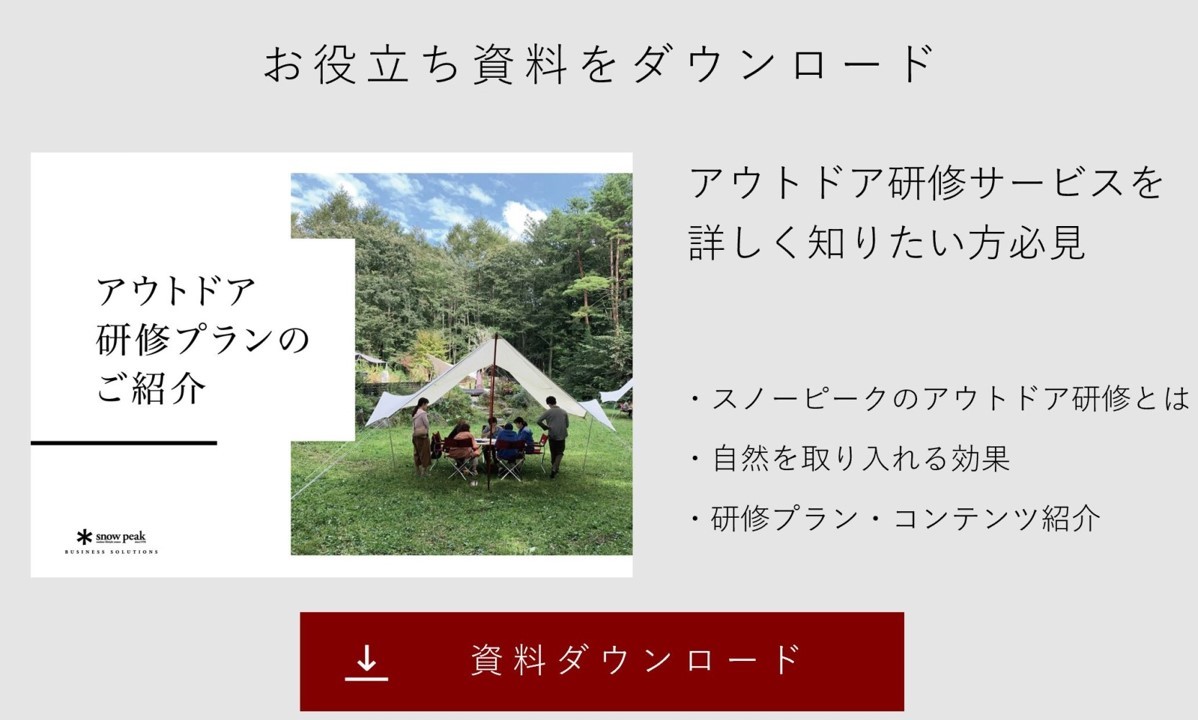トヨタ自動車株式会社のクルマ開発センターに属し、クルマの色彩から素材、音や香り、イルミネーションまで、五感に響く上質な体験をトータルでデザインする、カラー&感性デザイン部様
部署内のより良い関係性の構築を目指し、6月下旬の2日間、愛知県岡崎市の乙川沿いに広がるCAMPING OFFICE OKAZAKIとCamping Office osoto Okazakiを舞台に、アウトドア研修を行いました。
今回は、パーソナルな対話を中心にカスタマイズしたプログラムの企画と運営を、スノーピークビジネスソリューションズがサポート。心を解き放ち互いをよく知るための時間が、クリエイティブな発想の土台となるコミュニケーションに変化をもたらしています。
お客様:トヨタ自動車株式会社 クルマ開発センター カラー&感性デザイン部
グループ長 岡本 桃子 様
(担当:スノーピークビジネスソリューションズ HRS事業部 鈴木駿平)

お客様に空間全体で体験価値をお届けするために
-ーーカラー&感性デザイン部さんの事業概要を教えてください。
トヨタ自動車株式会社は、電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車など、マルチパスウェイで多種多様なクルマを開発してきました。そして、世界を牽引するモビリティカンパニーとして、常に新しい挑戦を続けています。
私たちカラー&感性デザイン部は、そうしたクルマを創造するクルマ開発センターのデザイン部門に属するペシャリスト集団です。クルマのペイントカラー、レザーや樹脂といった内装素材のコーディネーションに加え、音や香りといった感性領域に訴えるような空間全体の体験価値をデザインしています。
大切にしているのは、造形だけではなく、言葉や機能では表せない情緒的価値をお客様にお届けすること。そこでカラー、香り、マテリアル、イルミネーションなど、それぞれの分野で高度な専門性を持つメンバーが集まって、新しいクリエイティブを生み出しています。

専門性の高いメンバーの間に生まれた“見えない壁”
---アウトドア研修を導入した背景を教えてください。
私たちの部署は、もともと業務に高い専門性が求められる上、拠点が複数に増えてから勤務先も在宅も含めて多様化し、出張も多いため、個々が独立して働くスタイルが当たり前になっています。その結果、「誰がどんな仕事をしているのか」が見えにくくなり、物理的な距離だけでなく、精神的な距離も生まれやすい状況にありました。
外国籍のメンバーもいますし、他社から研修で来た方の入れ替わりも頻繁です。週1回は全員が顔を揃える機会を設けてはいますが、対話の機会が少ない状況に変わりはありません。それが積み重なったせいか、簡単なことでも「誰に相談すればいいのかわからない」、相手の苦労が見えないため「自分だけが大変……」といった様子がうかがえ、部署内の関係性に“壁”が生まれていることを肌で感じていました。
人と人を結ぶ線のつながりが細くなり、精神的なストレスも生まれているかもしれない。そんな危機感を抱くようになり、“見えない壁”を突破するブレイクスルーのきっかけが欲しいと考えていたんです。そんなときにスノーピークビジネスソリューションズ(以下SPBS)さんのご担当者と出会い、アウトドア研修に興味を持ちました。


人を知り、深いコミュニケーションが生まれる時間へ
---どのような研修内容にするか検討したプロセスを教えてください。
当初は、それぞれが専門性を持つスペシャリスト集団だからこそ、業務をシェアすることで単に1+1=2になるのではなく、「こんなこともできるのでは?」と相乗効果につなげ、新しいケミストリーを生み出せたら、と考えました。そこで、シナジーアップのきっかけとなるようなワークショップができないか、とSPBSさんにご相談させていただいたのが始まりです。
その後、話し合いを重ねる中で、業務シェアではなく専門性の違いを越えて、まず人を知ることが大事なのではないかと思い至り、研修のテーマは“人を知ること”に特化。SPBSさんの既存プログラムをベースに、パーソナルな対話を中心とした内容へとカスタマイズしていただきました。また、一度に全員が集まると関係性が希薄になりやすいとの懸念をいただき、部員全員を2チームに分けてそれぞれ実施。コンパクトな人数で、より深いコミュニケーションを育むことに注力しようと計画しました。
場所は、岡崎の乙川沿いにあるキャンピングオフィスに。まさに「都会と自然の境界」にある開放的な空間で、とても魅力的でした。自然に囲まれていながらもアクセスが良く、キャンプ未経験のメンバーでも身構えることなく参加できると考えました。


距離を縮めて会話を可視化し、想いを伝える時間に
---当日の研修内容や印象に残っていることを教えてください。
当日は、梅雨の時期なので雨を心配していたところ、まさかの猛暑日。その中でもSPBSさんが臨機応変に内容を調整してくださり、午前は風が抜ける乙川沿いのスペースで、午後は屋内の涼しいキャンピングオフィスで研修を進めました。
最初に挑戦したのは、言葉を使わない体験型アクティビティです。部署には英語しか話せないメンバーもいるため、「言語の壁を感じさせない内容にしたい」と希望したのですが、ご提案いただいたブラインドウォークやフラフープを使ったアクティビティは、体を使って自然にメンバー間の距離を縮めることができ、笑い声の絶えない時間になりました。
午後は、会話のキャッチボールを可視化するデモンストレーションからスタート。続いて、自分の経験を紙に書き出し、1on1で自分について話す練習をした後、3~4人の小グループでさらに深い話へと展開していくステップを踏みました。
夕食後は、屋外で焚火を囲んで一日の振り返りをシェア。仕事では見られないやわらかな表情が広がり、普段は無口なメンバーが、自分の想いを丁寧に言葉にする姿も印象的でした。外国籍のメンバーは「海外ではチームビルディングを行っている企業は多いが、日本では珍しい取り組み。実施してくれてありがたい」と大喜び。また「自分の存在をあたたかく受け止めてくれて、この場に自分がいることを認められたことが嬉しかった」と打ち明けるメンバーもいて、みんなでグッと感じ入る場面もありましたね。

部署の空気が変わり、コミュニケーションにも変化が
---研修に対する皆さんの感想や研修後の変化を教えてください。
すべてのプログラムが印象的でしたが、特に会話のキャッチボールのデモンストレーションで、会話の可視化ができたことが良かったと感じています。実際にボールを投げ合うシンプルな動作なのに、投げ方、受け取り方が人によって大きく違う。受け取らない場合も、そこには理由があるわけで「普段の会話でも起こりうることだ」と、メンバーは大きな気づきを得たのではないでしょうか。
また、今回の研修を通じて伝えたかったのは、「設定された場に参加する」のではなく、「一人ひとりが場をつくる」という意識です。その意図もメンバーにきちんと伝わり、研修後は日々のコミュニケーションの質と量が変化しています。実際、多くのメンバーが「話しかけやすい雰囲気ができた」「これまで壁を感じていた相手にも自然に声をかけられるようになった」と感じているようですし、「自己肯定感が上がった」「このチームで働けて良かった」という嬉しい声も寄せられました。
さらに、思わぬ収穫だったのは、このアウトドア研修が内省の機会にもなったことです。日々の業務に追われる中で見失いがちな、自分自身が大切にしている価値観やどういう自分でありたいかという展望を、一人ひとりが改めて考えることができました。
人と人とのつながりが生まれ、見えない壁が消えていくことで、部署全体のエンゲージメントが高まり、モチベーションが上がっていく。それが、結果的にクリエイションの質の向上にもつながる、と確信しています。


自分たちで“場”をつくる文化を育てたい
---今後の展望について教えてください。
アウトドア研修は、部署内の関係性を深める大きな一歩になったと実感しています。メンバー一人ひとりに対する解像度が上がったことで、誰かが困っている時やアウトプットがうまく出てこなかった時も、「あの人なら、きっとこういう理由があるのだろう」と、考えを巡らせることができるようになりました。専門性が高いデザイナーたちが、互いを知ることで生まれるシナジーアップ。そこに必要な基礎の再構築ができたと思っています。
また、部署の運営サイドでもロゴをつくったり、お揃いのネッククーラーを用意したり、お互いを知るきっかけとしてチェキで写真を撮って飾ったりもしました。「より楽しい時間にしよう」とアイデアを出して工夫し、参加者とコミュニケーションを取りながら研修をやり遂げた経験は、運営メンバーの成長にもつながったと感じています。
今回、SPBSのファシリテーターの方の場づくりが素晴らしく、参加者が自然に心を開けるような空気感をつくってくださいました。理想としては、こうした場を今後は内発的につくり出せる文化を育てていきたいと考えています。次はプロジェクト単位やセクション横断で取り組んでもおもしろいでしょうし、いずれは全員で集まる機会もつくりたい。小さな取り組みでも継続することで、私たちなりの場を生み出せるように、つながりを太く強くしていきたいですね。