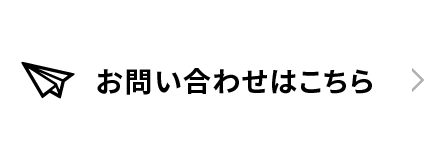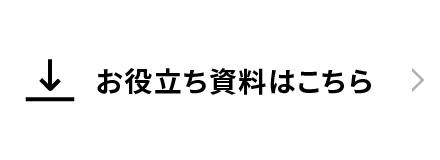急速に進むDXの波の中で、AIを活用した業務プロセスの最適化や、従来にない価値を生み出すビジネスの創出が、企業成長のきっかけとして期待されています。その中でも「生成AI」は、文章や画像、音声などを人間の手を介さずに生成する技術として急速に普及が進んでいます。
本記事では、まず生成AIと従来のAIの違いを整理しつつ、代表的なサービスや法人企業として押さえておくべきメリット・デメリットを解説します。また、無料の生成AIサービスを利用するデメリットを踏まえ、Microsoft 365 Copilotを活用する意義についてもご紹介します。
生成AIとは?
法人企業が知っておくべきメリットと導入時の注意点

01.従来のAIと生成AIの違い
従来のAIの特徴
従来のAIは、過去のデータから「パターン」を学習し、そのパターンを基に予測や判断を行うものが中心でした。具体的には、画像認識や需要予測などが代表例です。たとえば、画像認識AIは大量の画像データをもとに「犬」「猫」「車」などのラベルを学習し、入力された新しい画像が何であるかを分類します。このように、従来のAIは基本的に「答えを推定」する用途で活用されてきました。
生成AIの特徴
一方、生成AIは、学習したデータをもとに新たなコンテンツを「作り出す」点が大きな特徴です。文章や画像、音声といった多種多様な形式に対応でき、ユーザーが与えた指示(プロンプト)に応じて内容を生成することが可能です。たとえば、文章生成AIを活用すれば、特定のテーマに関する記事やアイデア、要約を瞬時に作成できます。従来のAIが「判断や分類」に注力してきたのに対し、生成AIは「創造的な生成」を行うため、より多彩なビジネスシーンでの活用が期待されています。
02.生成AIとは何か?その技術とメリット
生成AIの技術的なポイント
生成AIのしくみを支えているのは、「大規模言語モデル(LLM)」と呼ばれる技術です。これは、インターネットなどにある膨大な文章データを学び、人が話したり書いたりするような自然な言葉を返してくれるものです。最近では、クラウドの性能が上がり、たくさんのデータをすばやく処理できるようになったため、この分野の進化が一気に進んでいます。
生成AIのメリット
- 業務効率化
チャットボットを導入すれば、問い合わせ対応や社内ヘルプデスクの効率を格段に向上できます。文章要約やレポート作成にも活用でき、従来かかっていた手作業の時間を削減できます。 - アイデア創出支援
新商品や新サービスの企画段階で、たたき台となるコンセプトを作成したり、複数の角度からアイデアを提案したりすることが可能です。 - コスト削減
ルーティン作業を自動化することで、人件費や外部委託費を抑えられます。特に文章作成やコンテンツ編集といった領域でのアウトソーシングコストを削減しやすい点が注目されています。
03.代表的な生成AIサービス
生成AIを語るうえで、最も知名度の高いサービスの一つが「ChatGPT(OpenAI)」です。2022年末のリリース以来、世界中のユーザーに利用されてきました。チャット形式で自然な文章を生成できることが最大の特徴で、最近は、驚くべきスピードでバージョンアップが行われており、最先端の機能を備えるようになっています。
ChatGPTの主なポイント
・自然な文章生成
日本語を含む多言語に対応しており、指示したテーマや文体に合わせた文章を短時間で作成できます。ビジネス文書や提案書の下書き、メール文面の作成など、さまざまな業務で活用しやすい点が魅力です。
・コード生成のサポート
エンジニアやプログラマーが使えば、具体的なコード例を提示してもらうことができます。実装のヒントを得たり、既存コードの改善点を探ったりする際に役立ちます。
・Q&Aとアイデア創出
チャット形式で質問すると、関連情報やヒントを瞬時に提示してくれるため、新しいアイデアの発想をサポートすることも可能です。商品企画や情報収集の初期段階で、とても便利に使えます。
04.無料の生成AIを利用する注意点
個人向けには無料版の提供があるため、誰でも気軽に試しやすいのが大きなメリットです。ただし、企業が実務で利用する場合には、機密情報を入力した際のセキュリティリスクや、サービス提供元のポリシーを理解したうえで使う必要があります。
セキュリティリスク
無料の生成AIサービスをそのまま使う場合、やり取りの内容(企業の機密情報など)が外部サーバーに送信される可能性があります。提供元のプライバシーポリシーや契約条件によっては、送信データが学習に利用されたり、第三者に開示されるリスクがゼロとは言い切れません。法人企業としては、情報漏えいやデータの不正利用につながる恐れがあり、慎重な運用が求められます。
コンプライアンスやガバナンスの問題
業種によっては、個人情報保護やデータガバナンスが厳しく求められます。無料の生成AIサービスでは、管理者が従業員の利用状況を一元管理しにくく、いつどこでどんなデータが入力されているかを把握しにくいことが懸念です。その結果、思わぬ情報漏えい事件や規制違反が発生するリスクが高まります。
ビジネス利用に伴うサポート体制の不十分さ
法人向けに特化したサポートがない場合、トラブルが発生した際の対応が十分に行われない可能性があります。サービス提供元の方針が急に変わり、機能や料金形態が予告なく変更されるリスクも否定できません。ビジネスの継続性を重視する企業にとって、こうした不確定要素は大きなマイナスとなります。
05.法人企業に有用なMicrosoft 365 Copilot
Microsoft 365 Copilotは、生成AIを活用して業務効率化を総合的に支援するツールです。
・Microsoft 365とのシームレスな統合
Microsoft 365 Copilotは、WordやExcel、PowerPoint、Outlookなど、企業が日常的に使用するOfficeアプリケーションと統合されている点が最大の特徴です。すでに使い慣れた環境の中で生成AIが利用できるため、導入ハードルが低いのはもちろん、データの扱いも一括管理が可能です。たとえば、Wordでの文章作成やPowerPointでのプレゼン資料作成を、Copilotのアシストで効率化することができます。
・セキュリティとガバナンスの強化
Microsoftが提供するエンタープライズ向けのセキュリティ基盤が利用できるため、情報漏えいやコンプライアンス違反のリスクを大幅に低減できます。機密情報や個人情報を含むドキュメントを扱う場合でも、組織のポリシーに沿ったアクセス権限の設定や監査ログの管理が行いやすいのがメリットです。
・法人向けサポートと安定したサービス
Microsoft 365 Copilotは法人向けソリューションとして設計されており、サポート体制やサービスのアップデート計画も充実しています。企業の利用ケースを想定したドキュメントやヘルプが整備されているだけでなく、将来的な機能拡張やバージョンアップも安定的に提供されることが期待できます。
・運用コスト削減とROI向上
Microsoft 365という既存のプラットフォーム上で動作するため、新たなツールを追加導入する場合と比べて、初期導入コストや管理負荷を抑えやすいのも大きな魅力です。また、Copilotによるドキュメント作成や分析の効率化が進めば、従業員がより戦略的な業務に注力できるようになり、最終的にはROI(投資対効果)の向上につながります。
06.まとめ
生成AIは、これまでにない速度と柔軟性で、企業の業務効率化やイノベーション創出に大きく貢献してくれる可能性を秘めています。しかし、無料版の生成AIサービスをそのまま利用するには、セキュリティリスクやガバナンス上の課題、サポート体制の不透明さなど、見逃せない注意点が存在します。
Microsoft 365 Copilotを活用すれば、既存のOfficeアプリケーションとの密接な連携や強固なセキュリティ機能により、情報漏えいや規制違反のリスクを下げて生成AIを使えるようになります。さらに、法人向けのサポートや継続的なアップデートも受けられるため、安心して長期的な運用が可能です。
これからの時代、生成AIをどう活用するかは、企業の競争力や業務効率を左右する重要なテーマです。ぜひ本記事を参考に、自社の環境や業務内容に合った形での導入を検討してみてはいかがでしょうか。ビジネスの新たな可能性を広げるためにも、信頼性とセキュリティを兼ね備えたMicrosoft 365 Copilotのメリットを積極的に活用していただければ幸いです。
以下のリンクより【機能紹介や導入支援をまとめた資料を無料でダウンロード】いただけます。